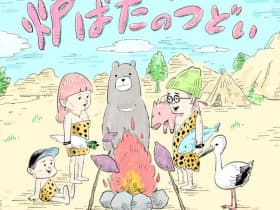二人を連れて歩く街~都会での子育てが教えてくれたこと~
双子と過ごした都会の時間
泣き止まない双子を抱きながら、私は「母」という役割の重さを初めて肌で感じていました。
豊岡では、ゆっくりと流れる時間の中で支えられながら母となり、
都会では、あまりにも早く過ぎていく日々の中で、夫婦でその重さとむきあいました。
思い返せば大変だったのは場所ではなく、都会で感じた“その速さ”だったのかもしれません。
双子の泣き声が重なる豊岡の夜。

▲里帰り出産~3か月の管理入院を経て~
夜中の1時。
実家の一室だけが明るく、ほかの部屋はしんと静まり返っていました。
「おぎゃあ、おぎゃあ」
泣き声が二重に響き始め、時計を見ると、まだ2時。
「あと4時間…」そうつぶやいても、
次のミルクの時間はもうすぐそこ。
ミルクを飲ませ終えると、また片方が泣く。
まるでバトンのように泣き声がつながり、子守唄と、赤ちゃんの泣き声だけが
夜の空気を揺らしているようでした。
朝になると母親が
「見とくから、少し寝たら?」といってくれる。
リビングから聞こえてくる母親のあやす声に「あぁ、やっとひと息つける」と眠りにつくことができる瞬間の安心感を今でも覚えています。
出産までの3か月間、私は管理入院をしていて寝たきりの時間も長く、すっかり体力が落ちてしまっていました。
母親の支えがなければきっとどこかで私の心は折れていたと思います。
けれどあの時間は,子どもたちと私が一緒に“生まれた”日々でした。

▲毎月お父さんが埼玉から会いに来てくれて、その時だけまとめて3時間の睡眠がとれていました。~双子用抱っこ紐~
近所を散歩すると、通りがかりの人が
「ありゃまぁ、双子ちゃん?」「大変だなぁ」と声をかけてくれたり、近所のおばちゃんが
「抱っこしてもええか?」と笑って手を伸ばし、他愛のない話がはじまる。
子どもから手が離れる、そんな何気ないその一瞬が私の心をふっと軽くしてくれたのです。

▲豊岡での子育て~シングルを連結できる横型ベビーカー~
夫婦ふたりだけの子育てが始まる
季節が春に変わる頃、保育園の入園をきっかけに、私たちは埼玉へ戻りました。
母親に「ありがとう」と言って豊岡を離れるとき、胸の奥がきゅっと縮むような不安がありました。
ここから、夫婦ふたりだけの子育ての始まりです。

▲家族そろって新幹線で埼玉へ・・・
外の音だけが聞こえていた
保育園が始まるまでは日中は私と子どもたち3人だけの時間。頼れる人もいない静かすぎる毎日。
外の世界の音だけが、ベランダの向こうからぼんやりと聞こえてきました。
「子育てって、こんなに孤独なんだ」
初めてそう思ったのは、この頃でした。
気づけば名前で呼ばれることも減り、母という役割にすべてが塗り替えられていく。
「私」という存在が霞んでいくような気がしたのです。
夫の帰りを待ちわびながら、時計を何度も見つめる。そんな毎日でした。
買い物や散歩に出るにも、気持ちの準備がいるようになりました。
外に出ることが、こんなにも勇気のいることだったなんて。
「迷惑をかけないようにと」
そんな思いが、いつしか日常の癖となっていました。
豊岡では、玄関を出るたびに誰かが声をかけてくれました。
「いってらっしゃい」「今日はあったかいね」
その言葉のない毎日が、こんなにも心細いなんて。
都会のペースはあまりにも早く、息を整える暇もないまま一日が過ぎていく。
まるで、自分だけが時間に取り残されているようでした。
保育園と、仕事への復帰
ようやく始まった保育園生活。
でも、慣らし保育の途中で息子がロタウイルスにかかり、一か月ものあいだ通園できませんでした。
それでも、職場復帰と同じタイミングでようやく保育園に預けることができました。
仕事復帰の初日。仕事の合間に寄ったカフェで一杯の珈琲を飲んだ瞬間、体の奥から息があふれ出すような感覚がしました。
「私、ずっと息を止めてたんだ」
ただ静かに座って珈琲を飲む―それだけのことが涙が出るほど沁みて、少しだけ気持ちがリセットされた気分でした。
それでも保育園に子どもを迎えに行くと、迎えてくれる子どもたちの笑顔に明日も頑張ろうと思えたのです。

▲子どもの笑顔に何度も励まされた。
都会でいちばん大変だったのは「移動」
埼玉での暮らしにはいつも“時間との競争”がありました。
とくに大変だったのは、子どもを連れての移動です。
私たちが暮らしていたのは、エレベーターのない二階建てのアパート。
ベビーカーは一階に置いてあったので、まずひとりを抱えて階段を降りベビーカーに乗せる。
それからまた階段を上がって、もうひとりを抱えて降ろす。
その往復を終えるころには、既に息が上がっていました。
電車やバスに乗るたびに、
「邪魔になっていないかな」「泣いたら迷惑かも」
そう考えるだけで心がぎゅっと縮こまる。
満員のバスを何台も見送り、空いた便を選びようやく乗った車内では「すみません」と小さく頭を下げながら、周囲にぶつからないよう気を張りつづけました。
誰かに何を言われたわけではないのに、いつの間にか自分で自分を小さくしていました。
都会で邪魔にならないように子どもを守っていたつもりが、いつしかまるでこの子たちが社会の中で“邪魔な存在”であるかのように、
自分が勝手に振る舞ってしまっていた。
そのことに気づいたとき、守るつもりだったのは子どもじゃなくて自分の心だったのかもしれないと、ぎゅっと胸の痛みを感じて
子どもたちに「ごめんね…」と繰り返しました。

▲豊岡で使っていた横型ベビーカーは 都会の狭い歩道を通れず、腰が座ったタイミングで縦型に買い替えました。
誰も悪くない。ただ少し速すぎただけ
きっとどこで子育てをしても大変なことはある。
けれど都会では、泣きそうな顔や疲れた顔が誰にも気づかれないまま過ぎていく。
“この街のリズムは、私には少し速いのかもしれない”と感じました。
都会が悪いわけではなく、きっと私はもう少しゆっくり歩ける場所のほうが向いていたのだと思います。
ふたごじてんしゃ
そんな時期に、コロナがやってきました。
外にも出られず実家にも帰れない。
世界がどんどん狭くなっていく中で、我が家に“救世主”がやってきました。
それが「ふたごじてんしゃ」。

▲「ふたごじてんしゃ」
公共交通に頼らずにどこへでも連れて行ってくれるこの自転車は、
私たち家族に新しい世界をくれました。
初めて近くの公園まで走った日、子どもたちは風を受けながら笑い続けていました。
夫がその横で「いいねぇ」と笑って、私も思わず笑った。
その瞬間、久しぶりに家族で心から笑った気がしました。。

▲ふたごじてんしゃで行った近所の公園
都会で見つけた小さな温もり
都会の暮らしは刺激があって、便利で、魅力もたくさんありました。
けれど、私たちの家族にはもう少し合う場所があるんじゃないかと思う瞬間が多々ありました。
それは人の多さよりも、心の余白の少なさに戸惑っていたのだと思います。
それでも、あの街で出会った人たちとのつながりは何よりの支えでした。
保育園で出会った家族や同じ建物の住人たちと、自然と声を掛け合うようになりました。
コロナ禍で外に出られない日々が続いても食材を分け合ったり、子どもの誕生日を小さくお祝いしたり。
そんな小さなやりとりの積み重ねが、私たちを支えてくれました。
家の前に集まって、子どもたちがシャボン玉を追いかける。
その後ろで、大人たちがマスク越しに笑い合う。
「あそこのデリバリー美味しいよ。」
「小さくなった服いる?」
そんな会話が、不安な日々のなかでいちばん心強く、
家族ぐるみで過ごす時間が増えるにつれ、“ここにも家族がいる”と思えるようになりました。
大変な時期を一緒に支え合い育った絆はどんな環境にも負けないほど温かくて、今でも私の宝物です。
そして、あの埼玉での日々があったからこそ、いま豊岡で過ごす日々を心から愛おしいと思えるのです。

▲大変な時期に支え合ったかけがえのない友人達と、移住前にみんなで遊園地(隠しちゃってるけど…みんな素敵な笑顔なんです!)
強さのかたち
いつかこの子たちも、進学や仕事で都会に出ていくでしょう。
それならせめて、今この時期だけでも自然の中で伸び伸びと、人とのつながりをあたたかく感じながら育ってほしい。
都会で生きる強さも大切だけど、まずは“自然の中で生きる強さ”を。
そして、助け合いながら生きる人の輪の中で自分を信じられる子に育ってほしいと思いました。
そんな願いを込めて、私たちは話し合いを重ね豊岡を選びました。
そして豊かな空気と、人のぬくもりに包まれながら、私たち家族の“豊岡での暮らし”が始まったのです。
あの時見失っていた「心の余白」を、いま豊岡でゆっくり取り戻しています。

▲保育園の最終日(豊岡に移住する日)テラスから皆が見送ってくれました。